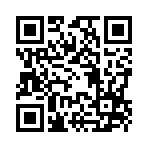雑賀崎の歴史

室町時代に、大阪、泉南の漁師が網漁業にきて、西の山の下のほうに家を2軒建てて、はじめて人が住むように成りました。その辺は、風当たりが少なくて家が波に流される心配の無い海岸であったからでしょう。だんだん人口がふえてくると東の方まで家が建ちました。江戸時代までは、村の中央部に畑や水田があったといわれます。江戸時代からは、一本釣りで遠くの海まで魚を釣りに行きました。田や畑の仕事は女の人だけでしました。田の浦までたんぼを作りに行った人もあったそうです。
山の上野もとの学校のあとあたりを城の内・どんべ(土塀)と呼びますが、戦国時代に雑賀党の見張り場があったからです。また、番所というのは、江戸時代の終わり頃、外国船などのあやしい船が通るのを見張るための番所のあとです。
この記事へのコメント
こんにちわ!雑賀崎にはひんぱんに行くのですが番所の意味も知らなかったのでみんなに自慢げに言ってやろうと思ってます^^その写真もいいですねー
Posted by 楠本マネージャー at 2009年08月13日 14:18
at 2009年08月13日 14:18
 at 2009年08月13日 14:18
at 2009年08月13日 14:18楠本マネージャー。始めまして
9・23の夕日を見る会は番所庭園と灯台でイベントを行います。
今日も箏の先生を案内して来ました。写真では島は2つに見えその間に夕日が沈みます。でも本当は4つの島があるんです。男島(おじま)・女島(めじま)そして双子島(ふたごです)これからも知ってる限りお知らせします。
9・23の夕日を見る会は番所庭園と灯台でイベントを行います。
今日も箏の先生を案内して来ました。写真では島は2つに見えその間に夕日が沈みます。でも本当は4つの島があるんです。男島(おじま)・女島(めじま)そして双子島(ふたごです)これからも知ってる限りお知らせします。
Posted by 和歌浦コモンセンス at 2009年08月13日 17:37